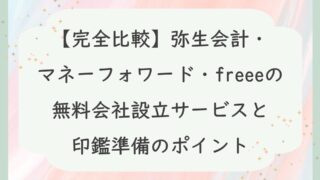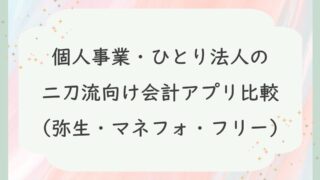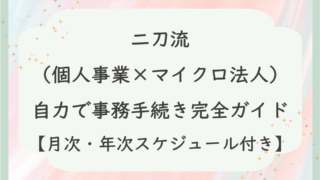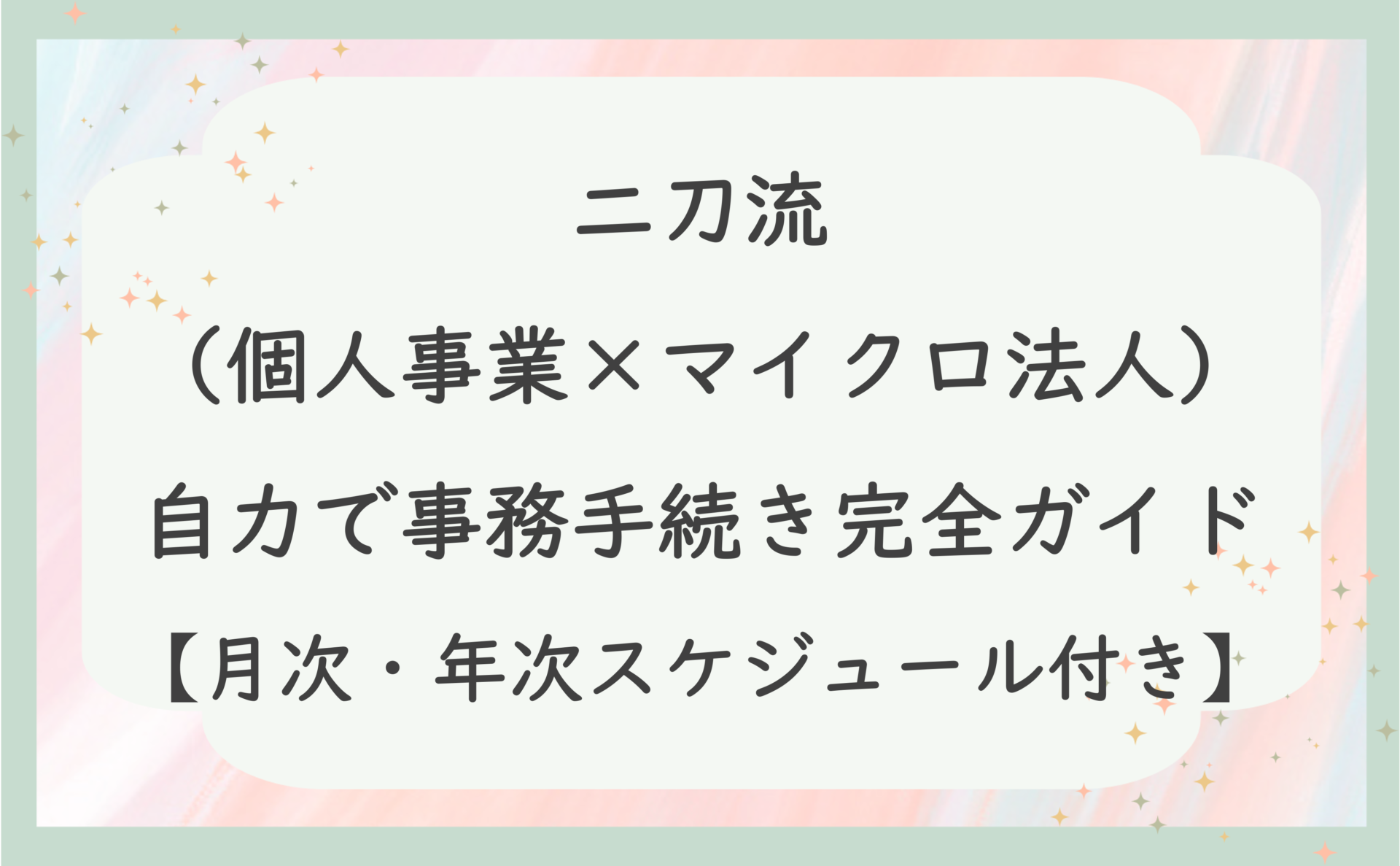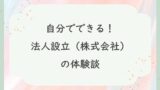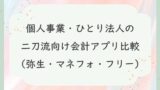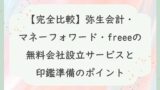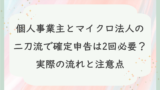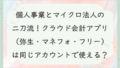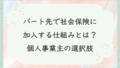個人事業主とマイクロ法人(ひとり法人)を同時に運営する「二刀流」。節税効果は大きいですが、「手続きが多くて大変そう…」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、私が実際に二刀流を自力で運営している経験をもとに、年間の事務手続きをすべて時系列でまとめました。
税理士や社労士に頼まず、自分で手続きをする方の参考になれば幸いです。
【前提】この記事の想定ケース
この記事は、以下のケースを想定しています:
- 役員報酬:標準報酬月額1等級になるよう設定(月額63,000円未満)
- 給与所得の源泉所得税:0円(月額88,000円未満)
- 住民税:普通徴収(天引きできないくらいに少額のため)
- 法人形態:株式会社
- 決算月:9月
- 役員:代表取締役1名のみ(従業員なし)
- 個人事業:青色申告、インボイス登録
- 法人:青色申告、インボイス未登録
【参考記事】
二刀流の年間手続きカレンダー
まずは全体像を把握しましょう。以下は、二刀流で必要な年間手続きのカレンダーです。
| 月 | 個人事業 | マイクロ法人 | <参考>個人住民税・普通徴収 |
|---|---|---|---|
| 毎月 | 日々の記帳、月次決算 | 日々の記帳、給与計算、社会保険料納付、月次決算 | – |
| 2〜3月 | 確定申告(所得税・消費税) | – | – |
| 6月 | 予定納税(第1期・対象者のみ) | 源泉徴収税納付(1月〜6月分) | 住民税(第1期) |
| 7月 | – | 算定基礎届 | – |
| 8月 | 個人事業税(第1期・対象者のみ) | – | 住民税(第2期) |
| 10月 | – | – | 住民税(第3期) |
| 10〜11月(決算月9月の場合) | – | 法人税申告、株主総会 | – |
| 11月 | 個人事業税(第2期・対象者のみ) | – | – |
| 12月 | 予定納税(第2期・対象者のみ) | 源泉徴収税納付(7月〜12月分)、年末調整 | – |
| 1月 | 年次決算 | 給与支払報告書、源泉徴収票 | 住民税(第4期) |
| 随時 | – | 事前確定届出給与(支給・変更時)、社会保険随時改定(該当時) | – |
※詳細は以下で解説します。
【個人事業】毎月の手続き
日々の会計帳簿への記帳
やること:
- 売上・経費をクラウド会計ソフトに入力
- 銀行・クレカ連携で自動取込
使用ツール:
- やよいの青色申告オンライン
 (セルフプラン)、マネーフォワードクラウド確定申告
(セルフプラン)、マネーフォワードクラウド確定申告
 (パーソナル)など
(パーソナル)など - 詳細:二刀流におすすめの会計ソフト
月次決算
やること:
- 当月の損益を確認
- 預金残高の確認
※月次決算の義務はありませんが、経営状況を把握するために実施することをお勧めします。
【マイクロ法人】毎月の手続き
日々の会計帳簿への記帳
やること:
- 売上・経費をクラウド会計ソフトに入力
- 銀行・クレカ連携で自動取込
使用ツール:
- 弥生会計Next
(エントリープラン)、
マネーフォワードクラウド会計
 (ひとり法人プラン)など
(ひとり法人プラン)など
給与(役員報酬)計算
やること:
- 役員報酬から社会保険料(本人負担分)を天引き
- 源泉徴収税の計算(役員報酬が低い場合は0円)
使用ツール:
- Excelなどで賃金台帳を自作する(備付の義務あり:年金事務所の調査で求められます)
社会保険料納付
やること:
- 健康保険料・厚生年金保険料を納付
- 口座振替
厚生年金保険料等・国民年金保険料の口座振替可能金融機関一覧表
納付期限: 翌月末日
所要時間: なし 厚生年金保険料等の納付は、口座振替(自動引落)が便利です!
月次決算
やること:
- 当月の損益を確認
- 預金残高の確認
※月次決算の義務はありませんが、経営状況を把握するために実施することをお勧めします。
【個人事業】年1回の手続き
確定申告・納税(所得税・消費税)
やること:
- 前年1月〜12月の所得を申告
- 所得税(3/15まで)・消費税(3/31まで)の納付
使用ツール:
必要書類:
- 青色申告決算書(会計ソフトで作成)
- 確定申告書(e-Taxで作成)
- 各種控除証明書(ほとんどがマイナンバーで紐付け済)
参考:
【マイクロ法人】年1回の手続き
株主総会開催・議事録作成(決算月から2ヶ月以内)
やること:
- 決算承認の株主総会を開催
- 議事録を作成・保管
参考: 株主総会の招集手続きは省略可能(J-Net21 ビジネスQ&A)
法人税申告・納税(決算月から2ヶ月以内)
やること:
紙媒体での申請(郵送・持ち込み)または電子申請
- 法人税・地方法人税・住民税・事業税の申告
- 消費税の申告(課税事業者の場合)
使用ツール(電子申請の場合):
- e-Tax e-Taxソフトのダウンロードが必要です(Windowsパソコンのみ)
- eLTAX PCdesk(DL版)のダウンロードが必要です(Windowsパソコンのみ)
提出書類(国税):
書式が郵送されないので、紙媒体申請の場合は国税庁ホームページから様式をダウンロードします。令和6年度から控えの返送対応をしてくれなくなりましたので、電子申請がお勧めです。
- 法人税及び地方法人税の申告(法人税申告書別表等)
- 令和7年4月以降に提供した法人税等各種別表関係(令和7年4月1日以後終了事業年度等分)
- 勘定科目内訳明細書(令和6年3月1日以後終了事業年度分)
- 法人事業概況説明書(税務署所管法人用)
- 適用額明細書(単体申告用)
提出書類(都道府県税・市区町村税):
地方税は書式が郵送されますので、紙媒体で郵送や持ち込みによる申請も、eLTAXで電子申請でもどちらでもいいと思います。
私の場合は最初は国税も地方税も申告書類を郵送していましたが、令和6年度に控え書類が返送されなくなったため、今年度(令和7年度)は国税だけe-Taxで電子申請、地方税は郵送し、来年度(令和8年度)は両方とも電子申請にしようと考えています。
年末調整(12月)
やること:
社内で作成・保管(7年間)
給与が低すぎて年末調整で精算できないので、各種の控除申告書は提出せず、個人の確定申告で精算します。
給与支払報告書・源泉徴収票(1月31日まで)
やること:
- 給与支払報告書を本人の住所地の市区町村に提出
- 給与所得の源泉徴収票を税務署に提出
- 給与所得の源泉徴収票を本人(自分)に交付
使用ツール:
参考:
算定基礎届(7月10日まで)
やること:
- 4月〜6月の報酬月額を届出
- 標準報酬月額を決定
使用ツール:
- eGov(電子申請)
- eGov利用にあたり、アカウントはGビズID(プライム)を予め取得します
- または郵送
参考:
【マイクロ法人】半年に1回の手続き
源泉徴収納付(6月・12月)
源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例を受けると毎月の続きが半年に1回になります。
やること:
- 所得税徴収高計算書
- 納付額が0円でも手続きが必要
納付期限:
- 1月〜6月分:7月10日まで
- 7月〜12月分:翌年1月20日まで
使用ツール:
【マイクロ法人】必要時に発生する手続き
事前確定届出給与を支給・変更する場合
やること:
- 役員賞与を支給する場合、事前に税務署へ届出
- 届出期限:株主総会から1ヶ月以内、または事業年度開始日から4ヶ月以内
使用ツール:
参考: 国税庁 事前確定届出給与
注意:
役員賞与を支払ったときは、社会保険の賞与支払届が必要です。
社会保険の随時改定(対象になる場合のみ)
やること:
- 役員報酬が大幅に変動した場合、標準報酬月額を改定
- 3ヶ月連続で固定的賃金が変動し、2等級以上変動した場合が対象
使用ツール:
- eGov(電子申請)
- eGov利用にあたり、アカウントはGビズID(プライム)を予め取得します
参考: 日本年金機構 随時改定
注意:
標準報酬月額1等級を維持する場合は随時改定はありません。
二刀流の手続きを効率化するコツ
1. クラウド会計ソフトを活用する
個人事業・法人の両方で会計ソフトを使うことで、記帳の手間を大幅に削減できます。
おすすめ:
- 弥生会計(個人:やよいの青色申告オンライン
 、法人:弥生会計Next
、法人:弥生会計Next)
- マネーフォワード(個人:マネーフォワードクラウド確定申告
 、法人:マネーフォワードクラウド会計
、法人:マネーフォワードクラウド会計

)
2. 電子申請を活用する
e-Tax、eLTax、eGovを使えば、自宅から申請・納付ができます。
3. スケジュール管理をする
Googleカレンダーなどで、手続きの期限を登録しておくと忘れません。
4. 無理せず税理士・社労士に頼むのもアリ
自力でやるのが大変な場合は、部分的に専門家に頼むのも選択肢です。
- 確定申告だけ税理士に依頼
- 社会保険手続きだけ社労士に依頼
など、柔軟に対応しましょう。
よくある質問
Q1. 二刀流の手続きは本当に自力でできる?
A. できます。特に役員報酬が低く、従業員がいない場合は、手続きがシンプルです。私も実際に自力で運営しています。
Q2. 手続きを忘れたらどうなる?
A. 期限を過ぎると、延滞税や過料が発生する場合があります。特に税務関係は厳しいので、期限管理を徹底しましょう。
Q3. 源泉徴収税が0円でも納付手続きが必要?
A. はい、必要です。納付額が0円でも「所得税徴収高計算書」を提出する必要があります。なお、法人税の納付額が0円の場合は「申告書類」は必要ですが、「納付書」の提出は不要です。
まとめ:二刀流の手続きは慣れれば簡単
個人事業とマイクロ法人の二刀流は、手続きが多いように見えますが、初年度は慣れないので大変だと思いますが毎年ほぼ同じ手続きですので、2年目からは簡単にお感じになると思います。
手続きのポイント:
✅ 毎月の記帳をサボらない
✅ 期限をカレンダーに登録
✅ 電子申請を活用
✅ 会計ソフトを使う
二刀流で節税しつつ、自力で運営したい方は、ぜひこの記事を参考にしてください!
【関連記事】
免責事項
この記事は、私が実際にマイクロ法人を自力で運営した経験をもとにまとめたものです。税制・社会保険制度は毎年変更される可能性があります。
- 最新の情報は、国税庁・日本年金機構・都道府県税事務所・各自治体の公式サイトでご確認ください
- 個別の税務相談は、税理士にご相談ください
- この記事の情報により生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません
※この記事の情報は2025年11月時点のものです。