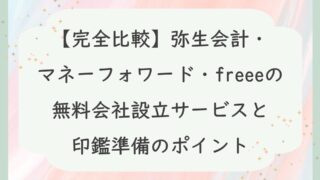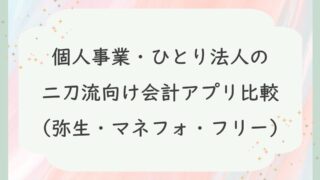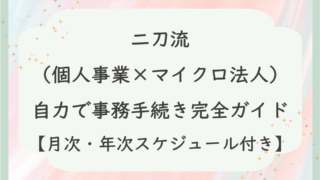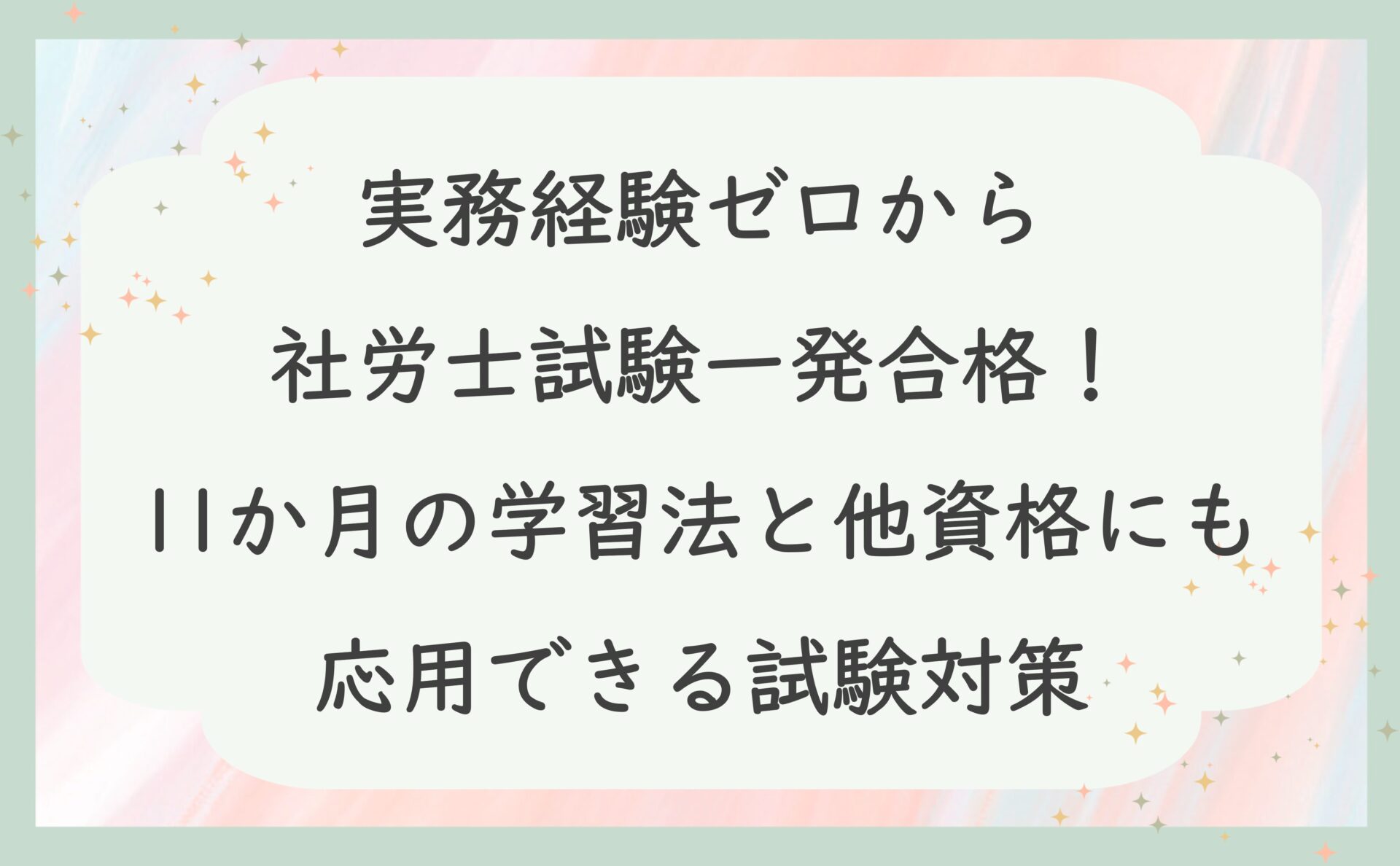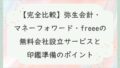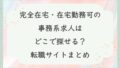社労士の受験勉強中です。勉強方法について何かアドバイスをしてください。

人事労務の経験ゼロから、通信講座と計画的な学習で社労士試験に一発合格した体験記です。11か月の勉強法や模試活用、健康管理の工夫に加え、他資格にも応用できる試験対策も紹介します。
実務経験ゼロからの挑戦
私は人事労務の経験がまったくない状態で、社会保険労務士試験の勉強を始めました。きっかけは「社労士は独立開業できる国家資格」という話を聞き、将来の選択肢を広げたいと考えたことでした。
周囲には「実務経験がないと厳しい」という声もありましたが、大手資格予備校の通信講座を活用し、約11か月間の本気学習で一発合格できました。
この記事では、2010年当時の学習法や生活習慣、反省点、そして他資格の受験にも応用できる普遍的な試験対策をご紹介します。
予備校の活用と学習計画
私が選んだのは、大手資格予備校のTACが提供する通信講座(DVD)でした。通信講座は、通学講座よりもDVD教材の到着が1〜2週間遅れるというデメリットがありますが、仕事や家庭の事情で決まった時間に通えない人にとっては非常に大きなメリットがあります。自分の生活リズムに合わせ、早朝でも深夜でも講義が受けられ、移動時間もゼロ。その分、学習時間を確保できるのは想像以上に効率的でした。
送られてくる教材は、基本テキスト、問題集、暗記ノート、横断学習用テキストなど多彩です。私はサブノートを作らず、テキストに直接書き込みをしながら学習しました。特に効果的だったのはアンダーラインの色分けです。初期は目立たない色で線を引き、復習や問題演習を重ねるたびに別の色を重ねていきました。最終的に濃い色が集中している箇所こそ、自分の弱点であり、試験直前に重点的に見直すべきポイントだと一目で分かります。
また、予備校からは教材とともに学習スケジュールが送られてきます。このスケジュールを基準に、私は常に2〜3か月先までの計画を立てていました。例えば「この時期までに労基法と労災法を2回転させる」「次の模試までに厚年法の横断整理を終える」といった具合です。計画表は机上に常に置き、毎日チェックを入れることで進捗が可視化され、やる気の維持にもつながりました。
通信講座には質問カードやオンラインフォーラムなどのフォロー制度もあり、分からない箇所はすぐに質問できる環境が整っていました。特に質問カードは、自分が何を理解していないのかを整理して書く必要があり、この過程で新たな気づきを得ることも多かったです。こうして、限られた学習時間を効率的に使いながら、着実に合格への道筋を描くことができました。

私はは資格予備校を使いましたが、受講料が約30万円でした。
受講料を節約したい方は、私が受講した予備校のTACから出版されている「2026年合格目標 社会保険労務士 独学道場【みんなが欲しかった!】フルパック+タテスタアプリ」で独学するのもアリだと思います。
私が受験するときもこういう独学で体系的に勉強できるツールが欲しかったです!今から2026年8月の受験に向けて行動しましょう!
2025年12月24日までキャンペーン価格49,500円(通常価格58,300円)15%OFF
書籍+Web講義+模擬試験+学習ガイドブック+質問メールと書籍を超えた充実した内容です!
詳しくはTAC出版の公式サイトをご覧ください!
学習スタイル:朝活と反復学習
私が学習を始めてから一貫して意識していたのは、時間帯による学習効果の違いです。特に平日は、「夜は暗記中心のインプット、朝は問題演習中心のアウトプット」という学習サイクルを固定しました。夜に覚えた知識を、翌朝すぐに問題を解くことで確認する。この流れを繰り返すことで、記憶の定着率が大きく向上しました。朝の時間は脳がリセットされ、前日の知識を整理しやすいので、アウトプット学習には最適です。
休日はまとまった時間を確保し、午前中に講義視聴、午後に答練や模試の演習、夕方に復習という流れにしました。この順番を崩さずに続けることで、講義で学んだことをすぐに演習で使い、その場で定着させることができました。特に復習は「その日のうちに」行うことを徹底し、翌日に持ち越さないようにしました。
過去問演習は、ただ繰り返すのではなく「なぜその答えになるのか」を説明できる状態を目指すことを意識しました。最低3回、多ければ5回は同じ問題集を回転させます。答えを丸暗記してしまうのは危険で、特に社労士試験では選択肢の細かい文言の違いが得点を左右します。「似た表現のどこが違うのか」を説明できるレベルまで仕上げることが大切です。
また、外出先や移動時間には、市販の一問一答形式のコンパクトな問題集を持ち歩きました。鞄からすぐに取り出せるサイズの教材は、細切れ時間を有効活用するうえで非常に役立ちます。こうしたスキマ学習の積み重ねは、最終的に大きな差となって表れます。
模試の活用と直前期の過ごし方
社労士試験の学習において、模試は単なる実力チェックではなく、本試験を想定した総合的なリハーサルの場です。私の場合、模試は5月から8月にかけて月1回のペースで受験しました。これにより、自分の知識レベルを確認すると同時に、試験当日の動きや時間配分までシミュレーションできました。
本番さながらの環境を整えるため、模試では持ち物・服装・昼食・飲み物まで本試験と同じ条件にしました。例えば、冷房対策のためにカーディガンを持参し、昼食はパンと野菜ジュースに固定。本番で「何を着るか」「何を食べるか」で迷う時間をゼロにし、精神的負担を軽減しました。こうした細部の準備は、一見小さなことですが、当日の集中力を保つために意外と重要です。
模試後の復習は、単に間違えた問題を確認するだけでなく、正解していても根拠があやふやだった問題も重点的に見直しました。社労士試験では「たまたま正解した」問題が本番では落とし穴になることがあります。私は模試後2〜3日以内に復習を終え、さらに1か月後に同じ問題を解き直す「二段構え」の復習法を取り入れました。この方法は記憶の定着を強化し、忘れやすい論点を再確認するのに効果的です。
直前期(7月〜8月)は、新しい教材や問題集に手を出さず、それまで使ってきたテキストと模試の復習に集中しました。直前期は焦りから新しい教材に手を伸ばしたくなりますが、それは知識を散らす原因になりがちです。私は予備校の「横断整理テキスト」と「暗記ノート」をフル活用し、会場にも携行しました。試験開始前のわずかな時間でも見返すことで、直前の確認が得点につながることもあります。
模試は成績だけを見て一喜一憂するものではありません。会場での時間の使い方や休憩時間の過ごし方、緊張感のコントロール方法まで含めて、本番の自分を再現するための重要な訓練です。社労士試験のような長丁場の試験では、こうした総合的な準備が合否を分けます。
健康管理とモチベーション維持
長時間にわたる学習生活では、知識を積み上げるだけでなく、体調と気力をいかに保つかが合格への重要な鍵となります。特に社労士試験は真夏の8月下旬に行われ、選択式80分、択一式210分という長丁場。集中力を最後まで維持するためには、日常的な健康管理が欠かせません。
私が意識したのは、まず腰痛や肩こりの予防です。受験勉強では机に向かう時間が長く、姿勢が固定されやすいため、1時間ごとに軽く立ち上がり、首や肩を回すストレッチを取り入れました。また、夜の勉強が終わった後や休日の午前中には軽いウォーキングを行い、体の血流を促進。これにより頭がすっきりし、学習効率も上がりました。
食事面では、糖質だけに偏らないようタンパク質やビタミンを意識的に摂取しました。特に試験直前の昼食は、模試で試した「パン+野菜ジュース」の組み合わせを本番でも採用。消化が軽く、午後の眠気を抑える効果がありました。水分補給もこまめに行い、真夏の試験当日には冷房による体の冷えにも対応できるよう服装を工夫しました。
モチベーション維持のためには、小さな達成感を積み重ねることが効果的です。私は1日の学習が終わるたびにチェックリストに✅を入れ、「今日もやりきった」という感覚を可視化しました。また、暗記カードや持ち歩き用の問題集にお気に入りのカバーを付け、少しでも楽しく取り組める工夫をしました。こうした小さなモチベーションを作る仕組みは、長期戦を乗り切る精神的な支えになります。
さらに、勉強の合間には自分へのご褒美を設定しました。たとえば、「今週は計画通り進められたら日曜の夜は好きなドラマを見る」など、学習以外の楽しみを適度に取り入れることで、燃え尽き防止にもつながります。
試験勉強は知識だけでなく、体力・気力・精神面のトータルマネジメントが必要です。健康とモチベーションを維持することは、最後まで走り抜くためのエンジンそのものだと実感しました。
反省点とやっておけばよかったこと
振り返ってみると、合格できたとはいえ「もっと早く手をつけておけばよかった」と感じる点がいくつかあります。その最たるものが一般常識科目の対策不足です。社労士試験の一般常識は出題範囲が広く、法律以外の労務管理や社会保障制度全般の知識も求められます。私は直前期に集中的に勉強しようと考えていたのですが、他科目の復習や模試対応に追われ、十分な時間を確保できませんでした。結果、本試験直後の自己採点では基準点に1点足りず、不合格を覚悟する事態に。幸運にも、その年は一部の設問が「没問」となり全員正解扱いになったため合格できましたが、これは完全に運がよかったと思いました。
もうひとつの反省点は、苦手科目の後回しです。私は労基法や労災法の内容に興味があり、自然と学習時間が多くなっていました。一方で健保法や国年法、厚年法は得意意識が低く、最初は後回しにしていました。しかし、演習を繰り返すうちにこれらの科目の方が得点源になりやすいと気づき、急いで力を入れ直しました。結果的には間に合いましたが、最初から満遍なく取り組んでいれば、もっと余裕を持って試験に臨めたはずです。
また、模試の復習方法についても改善の余地がありました。当初は間違えた問題だけを見直していたのですが、後半になってからは「正解したが根拠があやふやな問題」も必ず確認するようにしました。このやり方を最初から実践していれば、理解の浅い部分をもっと早く消化できていたと思います。
さらに、教材選びの慎重さも大事だと学びました。私は直前期に新しい問題集を購入することを避けましたが、逆に必要だった教材を早めに導入しておく判断力も必要です。特に一般常識対策の市販問題集は、もっと早く入手しておけば本試験での不安が減ったはずです。
試験は「限られた時間で最大の結果を出す戦い」です。後回しや油断が命取りになることを痛感しました。これから受験する方には、苦手科目や広範囲科目こそ早期着手し、得意不得意のバランスを常に意識してほしいと思います。
これから受験する方へのアドバイス(他資格にも応用できる試験対策を含む)
これから社労士試験に挑戦する方にお伝えしたいのは、実務経験ゼロでも合格は十分可能だということです。私自身、人事労務の知識が全くない状態から、通信講座を軸に11か月の集中学習で一発合格できました。大切なのは、正しい方法で学び、計画を継続することです。
そのためのポイントは大きく4つあります。
1つ目は、学習サイクルの最適化です。インプットとアウトプットを短期間で往復させることが記憶定着の近道です。講義やテキストで理解した内容をすぐに問題演習で確認し、間違えた箇所や根拠が曖昧な箇所はその日のうちに復習します。この「理解→演習→復習→再演習」の繰り返しは、社労士試験だけでなく、他資格試験や語学学習にも効果的です。
2つ目は、過去問の徹底活用です。過去問は出題傾向を知るだけでなく、解答の根拠を説明できるまで繰り返すことが重要です。私は最低3回、多いものは5回以上繰り返し、間違えた問題はもちろん、正解でも根拠があやふやなものを重点的に復習しました。この方法は、他の資格試験でも高い効果を発揮します。
3つ目は、スケジュール管理と朝活の活用です。予備校のカリキュラムを基準に、自分の生活に合わせて細分化した計画を立て、進捗を毎日可視化します。特に朝活は、計画を守りやすくする有効な手段です。仕事や家事に左右されにくい朝の時間を「学習の固定枠」として確保することで、安定して学習時間を積み重ねられます。たとえ30分でも毎朝継続すれば、年間で大きな差がつきますし、一日のスタートで勉強を終えた達成感が、その日のモチベーションにもつながります。
4つ目は、健康管理とモチベーション維持です。資格試験は長期戦ですから、体調不良や精神的な消耗は大きなリスクになります。こまめなストレッチや軽い運動、バランスの良い食事、十分な睡眠を確保しましょう。モチベーションは、小さな達成感を積み重ねることで維持できます。学習記録にチェックを入れる、ご褒美を設定するなど、継続できる仕掛けを用意することが大切です。
これらの方法は、社労士試験に限らず、他の試験にも通用します。正しい学習法、柔軟な計画、過去問反復、朝活、健康的な生活を組み合わせることが、合格への最短ルートです。
おわりに
振り返れば、社労士試験の学習は単なる資格取得のための努力ではなく、自分自身を管理し続ける長期プロジェクトのようなものでした。実務経験がなくても、大手予備校のカリキュラムに沿って計画的に学び、日々の積み重ねを続ければ、一発合格は決して夢ではありません。
この11か月間で学んだのは、知識だけではありません。限られた時間をどう使うか、モチベーションをどう保つか、体調をどう維持するか。これらはすべて、資格試験だけでなく、仕事や日常生活にも活かせるスキルです。特に、朝の集中時間を活かす「朝活」や、過去問を何度も回して根拠まで押さえる反復学習、模試で本番を再現する習慣は、他のあらゆる試験やプロジェクトにも応用できます。
また、合格をゴールに設定するだけでなく、「今日やるべきこと」を明確にして一つずつ達成していくことが、最終的に大きな成果につながると実感しました。学習計画はあくまで道しるべであり、状況に応じて修正しながらも歩みを止めないことが大切です。
これから受験する方へ。試験は確かに厳しい戦いですが、その過程は自分を成長させる貴重な時間です。合格証書を手にした瞬間の達成感は、長い努力のすべてを報いてくれます。どうか、日々の一歩を大切に、最後まで諦めずに走り抜けてください。
皆さんの挑戦が実を結び、来年の合格者名簿に名前が載ることを心から願っています。

独学で挑戦される方には「2026年合格目標 社会保険労務士 独学道場【みんなが欲しかった!】フルパック+タテスタアプリ」をお勧めします!
私が受験するときもこういう独学で体系的に勉強できるツールが欲しかったです!今から2026年8月の受験に向けて行動しましょう!
2025年12月24日までキャンペーン価格49,500円(通常価格58,300円)15%OFF
書籍+Web講義+模擬試験+学習ガイドブック+質問メールと書籍を超えた充実した内容です!
詳しくはTAC出版の公式サイトをご覧ください!