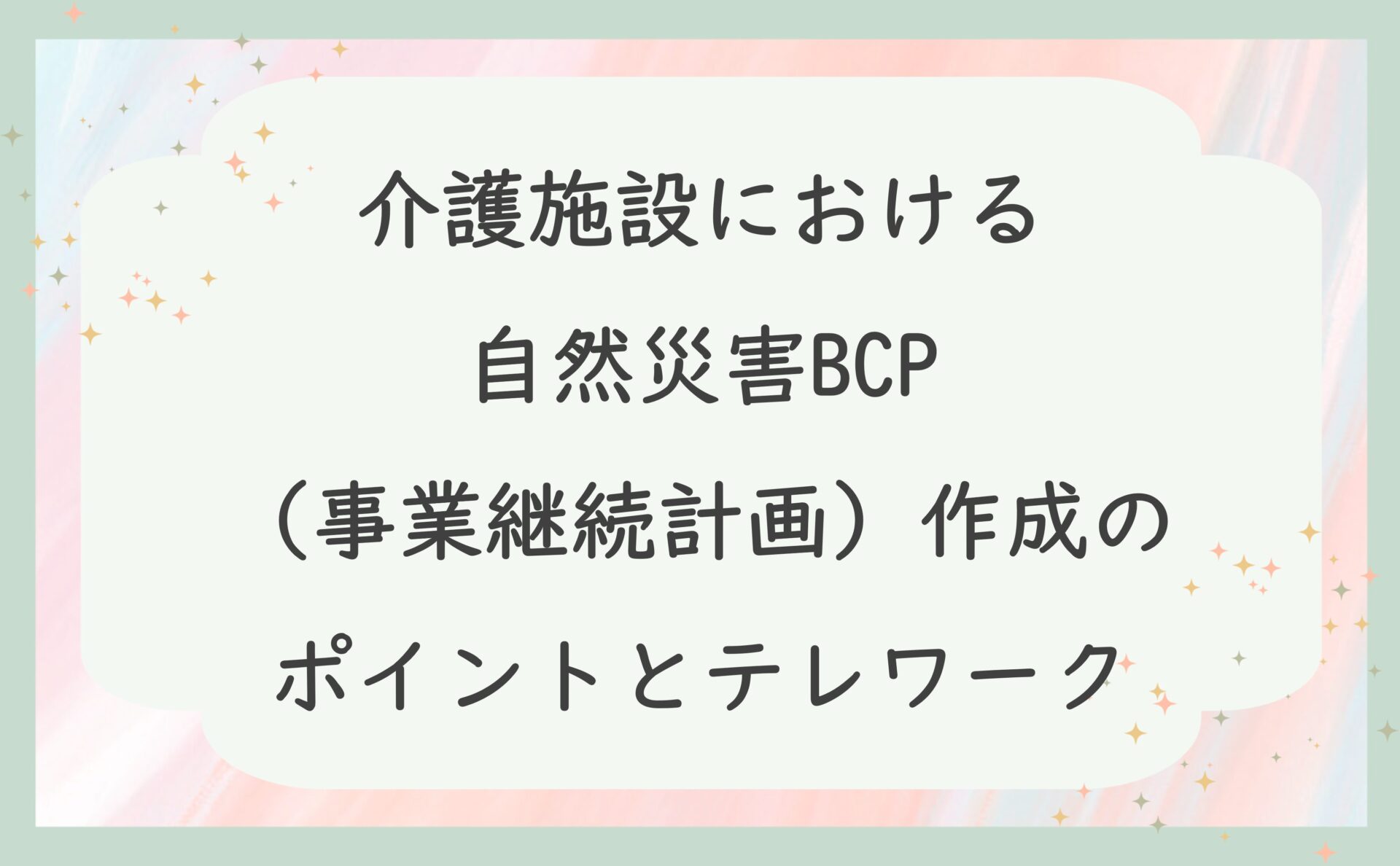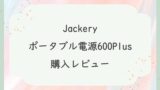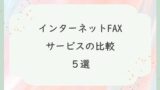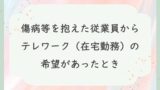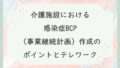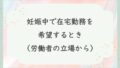ある介護施設からの相談です。

地震、水害などの各災害に対して、施設から職員に向けて定期的に教育研修しています。BCP作成義務化を契機に、これまでの情報を整理した上で、自然災害発生時のBCPを策定したいです。
最近、地震や異常気象による自然災害に対するBCPへの関心は益々高まっていると感じます。
さらに、介護事業においては業務継続に向けた計画(BCP)等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等が義務付けられるようになりました。ただし3年間の経過措置期間がありますので、遅くとも令和6年度からはBCPの整備が必要になります(「令和3年度介護報酬改定の主な事項について」厚生労働省)。
このため厚生労働省老健局から「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン(令和2年12月)」とともにBCP・様式例が公表されています。
この記事では主に施設系(入所系)介護施設におけるBCP策定と災害対策としてのテレワークの導入について解説します。
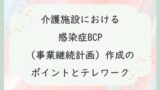
介護施設における自然災害BCP(事業継続計画)作成のポイントとテレワーク
BCPの策定から教育訓練までは次の5つのステップで進めます。
- STEP1 BCPの目的と推進体制を決める
- STEP2 被害想定と事業継続に重要な業務の選定
- STEP3 早期復旧戦略・代替戦略
- STEP4 マニュアル作成
- STEP5 教育・訓練
それでは順番に解説します。
STEP1 自然災害BCPの目的と推進体制を決める
自然災害BCPの目的
重要業務の継続・早期開始
- サービスの継続
- 利用者の安全確保
- 職員の安全確保
サプライチェーンでの対策・対応
変化する経営環境に対する適応力の強化
自然災害BCP適用範囲
- 組織|社会福祉法人○○ ○○センター
- 施設|本社(所在地 ○○…)
事業所(所在地 ○○…)
など - 事業|介護保険事業
障害者支援事業
など - 資産|上記事業にかかわる全従業者および各種施設設備
- など
BCP発動基準
【原因事象】
- 地震の震度階級(0,1,2,3,4,5弱,5強,6弱,6強,7の10階級)のどの階級にするか
- 大雨、防風、高潮、波浪、暴風雪、大雪、洪水の警報・特別警報のどの基準(気象庁 警報・注意報発表基準一覧表)にするか
- その他の脅威による事業中断の危機が起こった場合にも対応
【結果事象】
- 事業継続に重要な施設設備や公共交通網の甚大な被害により、施設設備が使えない、職員が出勤できない場合
- サプライチェーン(物資・インフラ・情報システムなど)において重要な関係先の事業が中断した場合
BCP停止基準
- BCP発動権限者による停止
体制の構築・整備(組織と役割)
- 全体の意思決定者
- 各業務の担当者(誰が、何をするか)
- 関係者の連絡先、連絡フローを整理する
STEP2 被害想定と事業継続に重要な業務の選定
被害想定
- 職員の出勤率(出勤人数)
- 職員・利用者の感染者数・濃厚接触者数
- 物資の供給が止まる(感染対策用の物品など)
重要業務(優先業務)の選定
考え方…Business Impact Analysis
- 収益(定量)
- 社会的影響(定性)
優先業務の考え方の例(ガイドラインより)
- 業務内容の調整
- 提供サービスを継続するか、変更するか?
- 居宅介護支援事業所や、保健所とよく相談したうえで、訪問時間を可能な限り短くする等、感染防止策に留意した上でサービス提供を行う
【事業影響度分析表】を作成しましょう!
ひな型・作成方法について
業務ごとの復旧の時間的許容限界を検討する
- 実現が望ましい目標復旧時間(利用者などの視点から)
- 実現可能な復旧時間
- 今後実施する対策による復旧時間短縮の見込み
ボトルネック分析
- ITシステム
- キーパーソン
- 施設・建物の必要性
- サプライチェーン
- 電力
- など
リスクアセスメント
(原因事象による被害の大きさ)×(発生頻度)×(発生確率)×(事業継続への影響度)
原因事象による結果事象(被害)
- 社員の出社不能(人員不足)
- 施設・建物の利用不能
- 情報システムの利用不能
STEP3 早期復旧戦略・代替戦略
早期復旧戦略
被害を少なくする対策
地震
- 耐震補強工事
- 耐震固定(転倒防止)
- ガラスの飛散防止フィルム
- 扉ひらき防止ストッパー
水害
- 重要物品を高い場所へ移動
- 止水板・土嚢(土不要で水につけて使うタイプがあります)
- 自動車などの高所への移動先の確保
- ブルーシート(被災前から備蓄しておきたいですね)
火災
- 建物の耐火性能向上
- 消火設備
- 初期消火訓練の実施
平常時の備え
電力
- 非常用電力の確保
- 自家発(燃料の確保も)
- 大容量ポータブル電源【2024年1月能登半島地震において、大容量ポータブル電源があったおかげで速やかな初動対応できた、との報道を見ました。ぜひご検討頂きたいと思います。】
- 電池、ポータブル電源
- エレベーター内防災イス(災害時閉じ込め対策の非常用備蓄品)
水
- 飲料水の備蓄
- 長期保存用の飲料水・飲料
- 非常用浄水器
- 給水タンク
- タンク車での水輸送の手配
- 節水(水のいらないシャンプー、歯磨きティッシュ、やぶれにくいタイプのおしりふき など)
ガス
- プロパンガス
- カセットコンロ・カセットガス
通信
- 衛星携帯電話
- Starlink(スターリンク)
- MCA(陸上移動通信システム)無線
- トランシーバー
- Wi-Fi
✓ ポケットWi-Fi
✓ 公共Wi-Fi(避難所・行政・コンビニ) - など複数の通信手段を確保
人
従業者・利用者の安全確保のための備蓄をしましょう。(休息場所の確保、健康・メンタル面にも配慮)
- ヘルメット・防災ずきん
- 睡眠(寝袋・防災エアーマット等)
- 長期保存食(非常食)、えいようかん(長期保存型ようかん)
- 非常用トイレ(携帯トイレ・簡易トイレ・仮設トイレ・備蓄用トイレットペーパー等)
- 防寒用品(非常用圧縮毛布、アルミシート等)
職員の出社判断
| パターン1 | パターン2 | パターン3 | パターン4 | パターン5 | パターン6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康状態 | 就労可能 | 就労可能 | 就労可能 | 就労可能 | 就労不可 | 就労不可 |
| 休業か勤務か | 休業 | 休業 | 休業 | テレワーク(在宅勤務) | 休業 | 休業 |
| 休業の原因・理由 | 会社の故意過失 | 経営・管理上の理由 | 不可抗力 | ー | 業務上の傷病 | 業務外の傷病 |
| 賃金支払い義務 | 賃金10割(民法第536条2項) | 休業手当(労基法第26条) | 賃金・休業手当不要(民法第536条1項) | 賃金10割(労基法第24条) | 休業補償(労基法第76条) | 賃金・休業補償不要(民法第536条1項) |
| 公的な所得補償 | ー | 雇用調整助成金 | (休業手当を支払った場合)雇用調整助成金 | ー | 休業補償給付(労災保険法第14条) | 傷病手当金(健康保険法第99条) |
介護事業所などの管理者には常駐が求められていましたが、この事務連絡により「管理上支障が生じない範囲内においてテレワークが可能」となりました。
さらに、インターネットFAXやIP電話の利用など、紙媒体での業務を電子化することにより、テレワークできる業務を拡大することができます。
復職判断
(原則)主治医の診断書兼意見書
代替戦略
- 職員の確保(法人内の調整、自治体・関係団体への要請)
- 代替業務拠点の確保(法人内・法人外、在宅勤務)
- 代替システムの確保(バックアップ構築、アウトソーシング活用)
- 代替調達先の確保(薬剤・防護具・消毒液等の備品)
- 代替調達先の安全性の評価(災害リスク・事業継続の備えの把握)
供給
- 自社で代替拠点を確保
- 同業他社と代替供給協定
必要物品の調達
- 代替調達先の確保
- 連携先の確保
入所者・利用者情報の整理
連携先、避難先施設でも適切なケアを受けることができるように、利用者情報を整理しましょう。
設備
- 設備の二重化(保有コスト・採算性の課題があります)
- 災害などで壊れやすい・入手困難な重要物品の代替を備蓄
ライフライン
- 電力
- ガス
- 水道
- 通信
- 代替調達先の確保が必要です
人材
- 重要ポストの代理者
- マルチタスク・クロストレーニング(業務マニュアルの整備)
- 自社以外の人的支援の調達先の確保(自社社員が行う業務と応援者が行う業務を決めておく)
代替調達先の安全性の評価
- 代替調達先の災害リスク・事業継続の備えの把握
マニュアルへ反映
これらを【初動復旧対応手順書】などの様式にまとめます。
STEP4 マニュアル作成
STEP1~STEP3で検討した内容をもとに、厚生労働省から公表されているBCP・様式例ひな型を改変します。
- 【BCPマニュアルひな型】自然災害発生時における業務継続計画 (介護サービス類型共通)
- 【様式1】推進体制の構成メンバー
- 【様式2】施設・事業所外連絡リスト
- 【様式3】職員、入所者・利用者 体温・体調チェックリスト
- 【様式4】感染(疑い)者・濃厚接触(疑い)者管理リスト
- 【様式5】(部署ごと)職員緊急連絡網
- 【様式6】備蓄品リスト
- 【様式7】業務分類(優先業務の選定)
- 【様式8】来所立ち入り時体温チェックリスト
- (ある方が良いと思います)職員配布用緊急携帯カード(中小企業庁HPより)
STEP5 教育・訓練
BCPを作るだけでは対策として不十分です。教育研修と実地訓練(シミュレーション)も義務化されています(「令和3年度介護報酬改定の主な事項について」厚生労働省)。
教育研修
- 災害の基礎知識
- 有事の際の初期動作
- コミュニケーションの方法
実地訓練
- BCP読み合わせ
- シミュレーション
- 実演テスト
教育訓練後のアンケート
- 改善
むすび
BCPのガイドラインや書式などは字が多すぎて読むのもうんざりするかもしれませんが、まずはひな型を改変して実際に読み合わせや実地訓練をしてさらにブラッシュアップするのが現実的だと思います。
BCPが机上の空論にならないよう、実際にBCPが機能することが重要だと思います。介護施設においてBCPとしてのテレワークのインパクトはそれほど大きくはないです。なぜなら対面業務が基幹業務であるからです。一方で、補助的な業務であればICTの活用によりテレワークで基幹業務を支援することができると思いますので、平時からICT化とテレワークの活用を進めて頂ければと思います。